
ピサンキから着想、細かい模様の絵付けが魅力!陶芸作家・飯野夏実さん【インタビュー】
目次
どんな技法が使われているの?
──飯野さんの作品には、どんな技法が使われているのでしょうか?絵付けの他にも色々ありそうです。
飯野さん 器の形作りは基本的に『ろくろ』ですが、たまに『タタラ』や『手捻り』の作品も作っています。装飾は『いっちん』という絞り出しの技法と、『下絵付け』と『上絵付け』の2種類です。

いっちん
──いっちんとはどのような技法なのでしょうか?
飯野さん 道具と材料があるので、実演してお見せしますね。いっちんは焼く前の乾き切っていない粘土の上に、泥状の粘土で模様を描く技法です。描いたあとに約950 ℃の温度で素焼きすると、粘土といっちんで描いた模様が密着して凹凸のある器に仕上がります。

四角い粘土の上に、細い線が描かれているのが見えるでしょうか?先端がとんがった入れ物の中に泥状の粘土が入っていて、絞り出すと写真のような細い線が描けます。お菓子のアイシングクッキーに似ていますね。
──お皿の表面に描いてある凹凸の線は、全部いっちんで施されたものなのですね。ちなみに、飯野さんが使用している粘土はどの種類のものですか?
飯野さん 私が使っている粘土は「磁器土」という種類のものです。この粘土は焼く前はクリーム色ですが、約900度の素焼きで薄いピンク色に、そして1250度以上の温度で本焼きすると白色に仕上がるんです。描いた絵や模様が映えるので、ずっとこの磁器土を使って制作しています。
──確かに、白い器の上に絵や模様が描いてあるとくっきりと綺麗に見えます!
絵付け
飯野さん 先ほど、「絵付けは『下絵付け』と『上絵付け』の2種類で描いている」とお伝えしましたよね?まずは下絵付けを実際にお見せします。

素焼きした器、下絵付け用の絵の具、筆、四葉の形の紙などが用意されました。
飯野さん 下絵付けとは、素焼きした器に描く絵付けの技法です。型紙のおもしろさと風合いをつけるために、『和紙染め』というやり方で描いています。やり方の流れは、
- 素焼きした器の上に、水を含ませた紙をペタッと貼り付ける
- 筆を使って、下絵付け用の絵の具を紙に染み込ませる
- 絵の具が素焼きの器に染み込んでいく
- 紙を剥がすと、くっきりとした模様ができあがる
こんな感じです。素焼きした器は水分をよく吸収するので、絵の具がしっかり染み込んでくれます。

絵の具を染み込ませてから紙を剥がすと、模様がくっきりと現れました!
飯野さん もう一つの上絵付けという技法は、釉薬をかけて本焼きをした器の上に描くという方法です。素焼きの器に釉薬をかけて本焼きを終えてから、ようやく上絵付けの技法に入れます。今ちょうどアシスタントが上絵付けをしているので、見てみてください。

──こちらのアシスタントさんが手に持っているものが、釉薬をかけて本焼きした器ですよね?
飯野さん そうです。器の表面がツヤツヤしていますよね?これが釉薬です。私が使っている釉薬は本焼きをすると透明になるもので、焼き上がりは磁器土の白がよく映えますし、絵付けの模様も華やかに見えます。
──色とりどりでとても綺麗ですね!上絵付けで模様が描き終わったら、次は何をするのですか?
飯野さん このまま上絵付けに触ってしまうと、せっかく描いた模様が剥がれてしまいます。なのでもう一度窯に入れて約800度まで上げて、器と上絵付けを密着させます。そうすると触っても剥がれなくなります。これで作品は完成です!
タタラ・手捻り

飯野さん 私は基本的にろくろを使って形作りをしているのですが、ろくろを使っていない作品もあります。これは機械(ろくろ)ではなく『タタラ』と『手捻り』というやり方で、粘土を自分の手や指先、道具で形を整えて作ったものです。いっちんや絵付けの技法も取り入れています。
このように、
- 形作りにはろくろ、タタラ、手捻り
- 素焼き前の器にはいっちん
- 素焼きした器には下絵付け(和紙染め)
- 釉薬をかけて本焼きした器には上絵付け
など、さまざまな技法が使われていました。作品のバリエーションも豊富で、見ていてワクワクします!
陶芸作家の過ごし方

──飯野さんの1日の制作時間はどのくらいでしょうか?
飯野さん 制作時間は特に決まっていないです。私の場合はお昼ごはんを食べ終えてから制作に入ることがほとんどですね。お昼から夜12時くらいまで、自分のペースで制作を続けています。陶芸の作品を作ることがほとんどですが、たまにピサンキやモザイクも作っていますよ。

──陶芸のお仕事がほとんどなのですね。これほど忙しいとお仕事を休むのが難しそうですが、お休みする日はご自身で決められているのでしょうか?
飯野さん 休日も特に決まっていないです。どこかへお出かけする日があれば、その日を休日として過ごします。
大変なことを上回る楽しさ

──陶芸作家の大変・楽しいことは何がありますか?
飯野さん 大変なことは、やっぱり経済面ですかね。普通のサラリーマンと比べると収入が安定していませんから。でも経済面の大変さを超えるくらい、制作が楽しいです!作品を作っていると「私にはこの道が合っている」と実感するくらい、今の活動が楽しいし自分に向いていると思います。
今後作りたいもの

──今後新しく作りたい作品はありますか?
飯野さん モザイクをもっとたくさん作りたいです。今は陶芸に比べて作る時間がほとんどないですからね。
──工房に飾ってあるモザイクは、どんな材料で作られているのでしょうか?
飯野さん モザイクは大理石やガラスなどを使っていて、細かく砕いて一粒一粒貼り付けています。適当な大きさに砕くのが意外と大変ですが、出来上がったときの感動は大きいです。次の個展では、できればモザイクも一緒に飾りたいなと思っています。

今後はモザイクもたくさん制作したいという飯野さん。個展で陶芸作品と一緒に飾られる日がとても楽しみです!

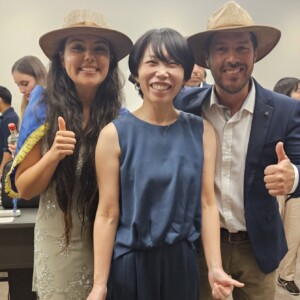




この記事へのコメントはありません。