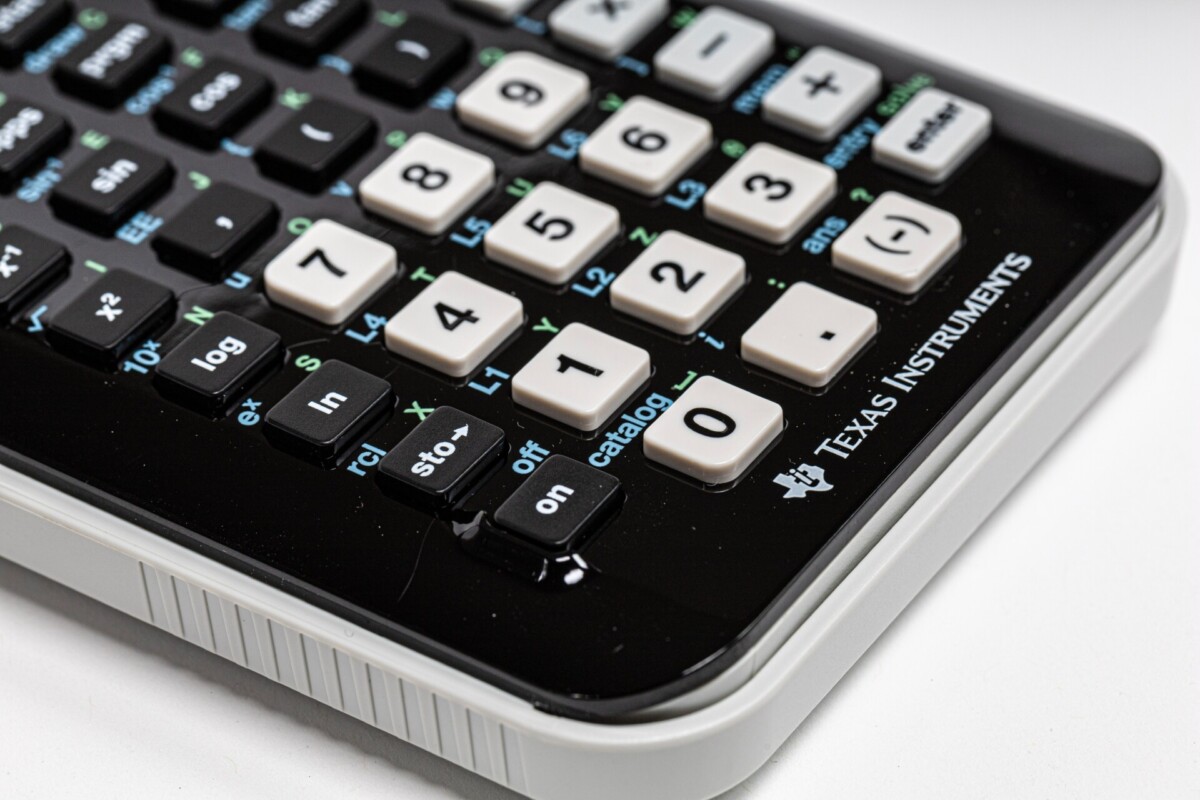
日商簿記検定の資格を取得する必要はない?【取得難易度と有用性を解説】
「大学生が取得したい資格ランキング」で、ほぼ確実に上位にランクインする日商簿記検定。
一般的には大学生の頃に取得が推奨される資格ですが、商業高校に所属していた筆者は、高校2年生で日商簿記2級を取得することができました。
本記事では、実際に日商簿記2級を取得した筆者が、資格の取得難易度や有用性について解説していきます。
目次
日商簿記検定は難しいの?
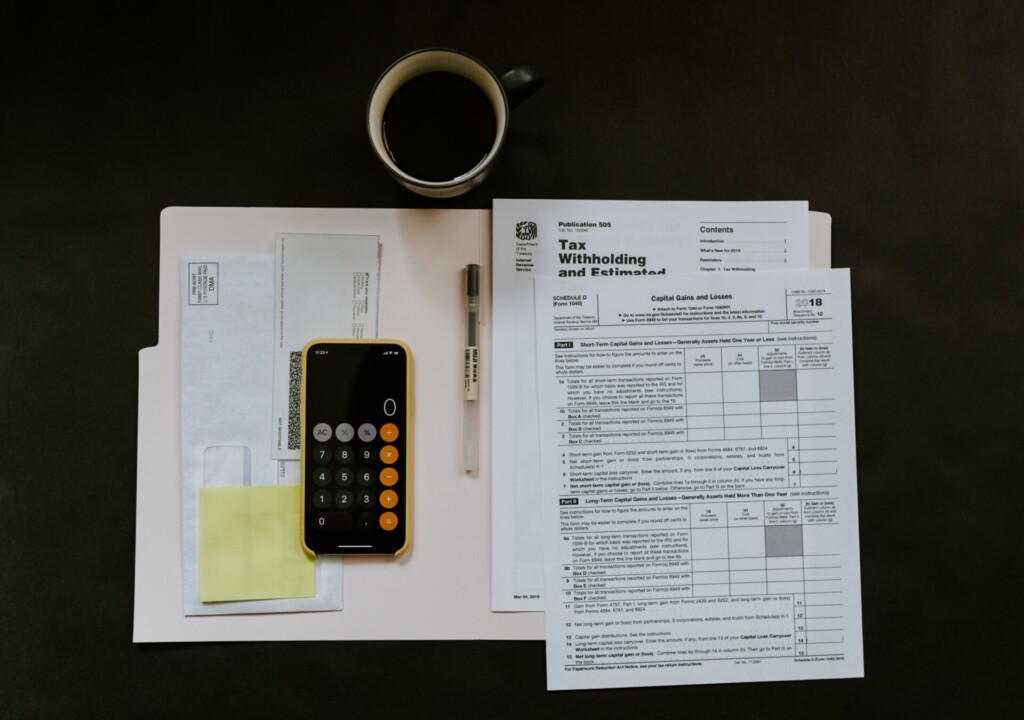
日商簿記検定は3級から1級まであり、それぞれで合格率が変動しています。一般的に3級は40〜50%、2級は20%程度、1級は10%程度だとされているようです。
また、ユーキャンの記事によると、合格に必要な勉強時間は3級が100時間程度、2級が250〜350時間程度、1級が1,000〜2,000時間程度とされています。
試験内容については、3級は暗記さえできれば合格できる内容ですが、2級は工業簿記という科目が加わることで複雑な計算が要求されるようになり、1級に関しては会計学や原価計算が試験科目に加わります。
以上のことから、会計士や税理士を目指すわけでないのであれば、3級または2級を目指すのが一般的な目標です。
日商簿記検定は就活に有利?
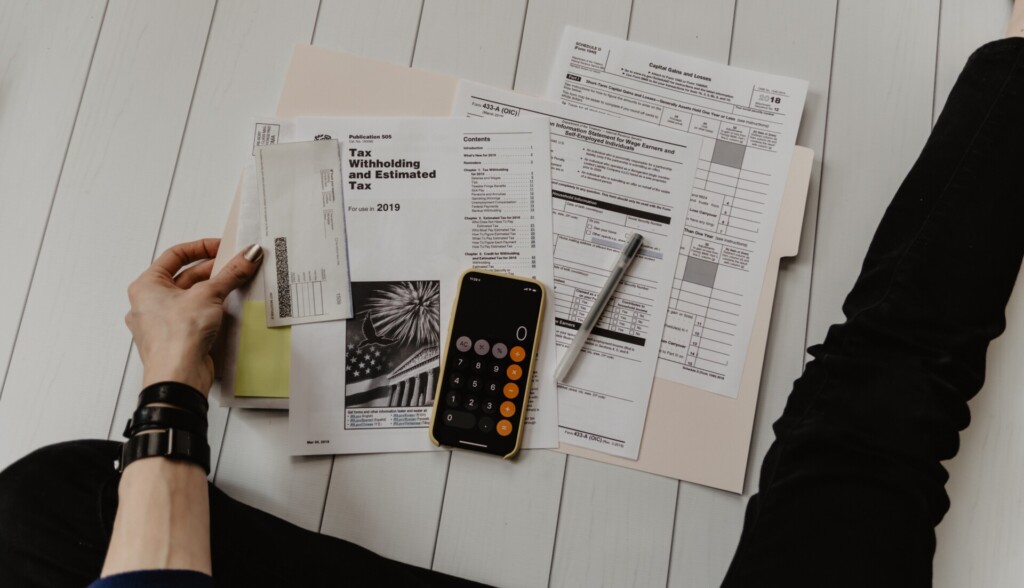
では、日商簿記検定は就活に有利なのでしょうか。
結論から言えば、それなりに有利です。あくまでも評価材料の一つとして、日商簿記検定は有効活用可能だといえるでしょう。
特に経理職や事務職を希望している場合は、日商簿記検定は有力な評価材料となります。この場合、日商簿記検定3級でも、十分な効果を発揮すると考えられます(もちろん等級は高い方がいい)。
ただし、「日商簿記検定を持っているから優秀」と判断されるわけではありません。特に自己PRとして日商簿記検定を活用する場合は、取得までのプロセスが魅力的である必要があります。
【個人的な意見】日商簿記検定は必要ない

これは個人的な意見ですが、日商簿記検定を取得する必要性はほとんどありません。その理由として、事務職や経理職のデジタル化が進んでいることがあげられます。
例えば経理職に関しては、freeeやマネーフォワードのようなクラウドサービスが発展しており、簿記の知識がそこまでなくても仕事をこなせるようになってきました。筆者は個人事業主なので、確定申告などでマネーフォワードを利用していますが、少なくとも資格を取得するレベルの簿記の知識は、ほとんど必要ないと感じます。
また、これは日商簿記検定に限った話ではありませんが、資格を持っているからといって実際にその知識を活用できるかどうかは別の問題です。
もちろん、現行の制度において公認会計士や税理士を目指したいのであれば、日商簿記検定1級が必要不可欠です。しかしあくまでも「就活で役立ちそうだから……」という理由であるなら、その時間を自分の好きなことに充てることを、筆者は強くおすすめします。
財務諸表と簡単な仕訳は知っておいた方がいい

日商簿記検定を取得する必要性はないと述べましたが、簿記の最低限の知識は理解しておくべきです。特に財務諸表と簡単な仕訳は、ビジネスマンであるなら必須の知識だといえるでしょう。
財務諸表
まず財務諸表が理解できるようになると、企業の財務状況が一目でわかります。
財務状況が理解できれば、就活や株式投資などで大いに役立つようになるでしょう。ちなみに筆者は、企業や国の財務状況を見て社会がどうなるのかを自分なりに未来予測してみるのが趣味です。
仕訳
そして仕訳が理解できると、確定申告で役に立ちます。
最近はふるさと納税の普及もあり、サラリーマンでも確定申告することが増えてきました。税理士に外注してもいいのですが、その場合は最低でも10万円ほどは必要です。最初はまず自分で確定申告するのがベターな選択になるでしょう。
確定申告というと難しい印象がありますが、freeeなどを活用すれば、仕訳をポチポチ入力するだけで確定申告書を作成することができます。
社会を生き抜くためのスキルとして、財務諸表と簡単な仕訳は抑えておくべきです。ちなみにこれらの基礎的な知識は、日商簿記検定3級を取得する必要がないほど簡単な知識なので、わざわざ勉強する必要はありません。
まとめ
筆者が商業高校に所属していた頃、なぜか簿記にとてもハマってしまい、その勢いで日商簿記検定2級を取得してしまいました。
しかし今こうして個人事業主となり、自分で確定申告していると「あ、資格は必要なかったな」と断言できます。それぐらいに現代は、デジタル化が進んでいるのです。
そしてこれは日商簿記検定に限った話ではありません。資格と呼ばれるものの大半は、ITによって必要性が薄れていくと考えられます。
「資格を取れば仕事には一生困らない」は、これからの変化の激しい時代では幻想にしか過ぎません。これについても、いつか深掘りして記事にしてみようと思います。

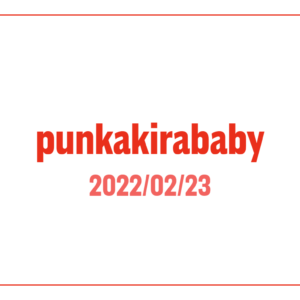




この記事へのコメントはありません。